足の爪が痛い、歩くとズキズキする──そんなときに疑われるのが「巻き爪」や「陥入爪(かんにゅうそう)」です。
これらは似たような症状を引き起こしますが、実は原因や治療方法が異なることをご存じでしょうか?
この記事では、巻き爪と陥入爪の違いをわかりやすく解説し、予防やセルフケアのポイントまで詳しく紹介します。
巻き爪とは?
巻き爪とは、爪の両端が内側に大きくカーブして、爪全体が丸まってしまう状態を指します。
爪が横方向に巻き込むことで、皮膚に食い込みやすくなり、痛みや炎症を引き起こすことがあります。
主に足の親指に発生しやすいのが特徴です。
巻き爪の主な原因
巻き爪の原因にはいくつかありますが、代表的なものは以下の通りです。
-
不適切な爪の切り方:深爪や角を切り落としすぎることで、爪が食い込みやすくなります。
-
靴の圧迫:先の細い靴やヒールなど、爪を押しつぶすような靴を履くことで発生しやすくなります。
-
歩き方のクセや外反母趾:体重のかけ方の偏りが、爪に過度な力を加えることがあります。
-
加齢・乾燥:年齢とともに爪の弾力が失われ、巻きやすくなる傾向があります。
巻き爪の症状
軽度では違和感程度ですが、悪化すると次のような症状が現れます。
-
爪の両端が皮膚に食い込み、痛みを感じる
-
爪の形がU字やC字状に変形している
-
靴を履くと圧迫されて痛む
-
爪の下に炎症や腫れが見られる
巻き爪自体は、爪の形の異常が中心であり、必ずしも炎症を伴うわけではありません。ここが、陥入爪との大きな違いです。
陥入爪とは?
陥入爪(かんにゅうそう)とは、爪の角や縁が皮膚の中に食い込んで炎症を起こしている状態を指します。
巻き爪が原因で起こることもありますが、陥入爪はあくまで「爪が皮膚に刺さり、炎症を起こしている病態」です。
陥入爪の主な原因
-
深爪:爪の角を短く切りすぎると、皮膚が爪に覆いかぶさり、次に伸びた爪が食い込むことで炎症が起きます。
-
外傷や圧迫:運動や長時間の立ち仕事、きつい靴による圧迫が原因になることも。
-
巻き爪の放置:巻いた爪の先が皮膚に刺さることで、結果的に陥入爪になります。
陥入爪の症状
巻き爪に比べて、陥入爪は炎症や化膿が起きやすいのが特徴です。
-
爪のわきの皮膚が赤く腫れる
-
押すと強い痛みがある
-
膿や出血が見られる
-
歩行が困難になるほどの痛み
このように、陥入爪は単なる見た目の問題ではなく、感染症を引き起こす危険性があります。
放置すると細菌が入り、肉芽(にくげ)と呼ばれる盛り上がった組織ができることもあります。
巻き爪と陥入爪の違いを比較
| 項目 | 巻き爪 | 陥入爪 |
|---|---|---|
| 定義 | 爪が内側に巻いて変形している状態 | 爪の角が皮膚に刺さり、炎症を起こしている状態 |
| 主な原因 | 深爪、靴の圧迫、加齢、歩き方の癖など | 深爪、外傷、巻き爪の放置 |
| 痛み | 軽度〜中等度(圧迫時に痛い) | 強い痛みや腫れ、膿を伴うことが多い |
| 見た目の特徴 | 爪がカーブしているが、炎症は軽い | 爪のわきが赤く腫れ、化膿していることが多い |
| 治療法 | ワイヤー矯正・テーピングなど | 抗生剤治療・爪の部分切除など |
治療法の違い
巻き爪の治療
巻き爪は、爪の形を矯正して再発を防ぐ治療が中心です。
-
ワイヤー矯正法:爪の表面に特殊なワイヤーを取り付け、少しずつ形を整えます。
-
テーピング法:皮膚を軽く引っ張ることで、爪が皮膚に食い込みにくくします。
-
爪の正しい切り方・靴の見直し:根本的な再発防止に欠かせません。
陥入爪の治療
陥入爪は、まず炎症や感染の治療を優先します。
-
抗生物質や消毒:炎症を抑えるために使用されます。
-
爪の部分切除(フェノール法など):食い込んでいる部分を取り除く処置。
-
肉芽の除去:化膿している場合は、膿を排出することもあります。
自宅でできる予防とケア
-
正しい爪の切り方
爪は「まっすぐ四角く」切るのが基本。角を丸くしすぎないようにしましょう。 -
サイズの合った靴を履く
つま先に少し余裕がある靴を選び、爪への圧迫を防ぎます。 -
足の清潔を保つ
毎日の入浴や足洗いで清潔を維持し、菌の繁殖を防ぎましょう。 -
歩き方・姿勢の見直し
正しい重心で歩くことが、爪への負担を減らすポイントです。
まとめ
巻き爪と陥入爪はよく混同されますが、巻き爪は「爪の形の異常」であり、陥入爪は「皮膚への食い込みと炎症」という明確な違いがあります。
軽度であればセルフケアで改善できますが、痛みや化膿がある場合は皮膚科や整形外科を早めに受診することが大切です。
爪は小さな部分ですが、トラブルが起きると歩行や生活の質に大きな影響を与えます。
普段から正しいケアを意識し、健康な足元を保ちましょう。
この記事に関する関連記事
- 初めての巻き爪矯正でよくある質問まとめ|痛み・回数まで専門家が徹底解説
- 巻き爪になりやすい人の特徴と改善のためのポイント
- 足のバランスの悪さとダイエットの意外な関係
- 【巻き爪の初期症状とは?】放置すると悪化する前に知っておきたい対処法
- 巻き爪は放っておいたら治る?専門家が教える正しい対処法とは
- 【巻き爪の治し方|自分でできる対策と注意点】京都・西院で巻き爪ケアなら当院へ
- 【巻き爪と陥入爪の違いとは?】京都・西院で足のお悩みなら当院へ
- 【巻き爪治療】痛みが怖い方へ|透明プレートでやさしく矯正する新しい方法とは?
- 外反母趾と巻き爪の深い関係|足の痛みを根本から解決するには?
- 巻き爪になりやすい人の特徴は?原因と予防法を徹底解説!
- 【巻き爪の原因、知っていますか?】あなたの足の悩み、治療院で改善できます!
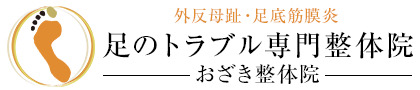
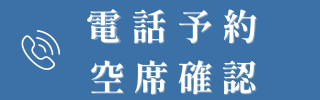
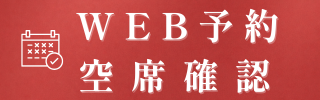





お電話ありがとうございます、
足専門整体 京都おざき整体院でございます。